こんにちは。ココです。今日は、教室の荒れについてお話します。
私は高校で教員として働いているのですが、荒れている教室の授業も受け持っています。荒れている教室とはどういった感じかというと、・教室が静かになる瞬間がない・先生に威圧的な態度で接してくる・授業中立ち歩く・授業中スマホを使う などです。荒れの程度はクラスによって変わってきますが、私が教科担当しているクラスは、上記に述べたことが全て当てはまります。ですが、問題行動を起こしている生徒が特定の何人かだけということと、先生とまだ会話ができるということからまだまだ諦める段階ではないと思い、手遅れになる前に生徒指導の勉強を始めようと思いました。今日は、今までの指導法と、今の指導法で生徒たちや私自身がどう変化したかをお話していこうと思います。
今までの私の指導方法
今までは、生徒たちにとにかくなめられてはいけないと思っていました。そのために、小さな生徒たちの問題行動にもしっかり指導してきました。小さな問題が積み重なり、大きな問題に発展していくことをとても恐れていました。後ほどお話しますが、この行動が荒れの原因を作っていたのだと今では分かります。叱るということはたくさんしていましたが、ほめることはしてきませんでした。叱ると、相手は先生に対して否定的な感情になるので、心に距離ができたり、口論に発展してしまったりします。もちろん叱ることは必要なのですが、心の距離の近づけ方を理解しないまま行っていたのが問題だったのだと思います。この時は、問題行動をつぶすことに焦点を当てていたので、そこまで気が回らないし、余裕がなかったです。
今の指導方法
今は、もちろん問題行動(授業中の立ち歩き、スマホ、暴言)に対して注意はするのですが、その方法を変えました。自分がどんな問題行動に対してどんな指導方法をとるのか、一貫したルールを作ることにしました。まず、スマホや、居眠りなど、直接他人の邪魔にはならない行動には、ジェスチャーでダメだよということを伝えるようにしました。まず目を合わせて、腕で大きくバツ印を作ったり、首を横に振ったりといった感じです。先生と信頼関係ができている子であれば、このジェスチャーで問題行動をやめてくれます。やめてくれない子の場合でも、やめるまで追求することはしません。いちいち小さなことで目くじらを立てていたら、口論に発展したり、生徒も意地になってこちらに対して攻撃的になるからです。追及はしませんが、見ているよということを毎回ジェスチャーで伝える必要はあります。では、どんな時に叱るときに本気さを伝えるかというと、他人に対して悪い言葉を使ったり、授業の邪魔になる行為をした時です。この時は「やめなさい」と少し大きめの低い声で言うようにしています。暴言や授業妨害(黒板に落書き・人のものを取り上げる)を放っておくと、それがどんどん学級の崩壊につながります。叱られた生徒は、かっとなり、あなたをにらめつけたり、暴言を言って来たりするかもしれません。それでも、決して動揺したりしないで、毅然とした態度をとることが大事です。目を見つめて先ほどのジェスチャーを使います。口論になる前にその子から離れましょう。その子が問題行動をとるのをやめてくれていたら、主導権はこちらにあるということです。やめない場合は、私の場合は、廊下にでて1対1で対話をするようにしています。例えば次のような感じです。「私がいつもあなたを叱っている理由が分かる?あなたがとてもいい子だからだよ。あなたがいつか自分で気が付いて、行動をゆっくりでも変えていけると思っているからあなたに怒ることがあるんだよ。そうじゃないと何も言わないよ。」といった感じで、目の前の生徒のことを認めながら心を解きほぐしていくことを意識しています。この1回の会話だけで、生徒は叱られることの意味の取り方を変えます。
ここまで叱り方についてお話してきましたが、如何にほめるかが一番重要です。ほめられる行動をとった時(発表できたとき・黒板を消してくれた時・ノートを一生懸命とっている時)にはすかさずその子のところに行って、ほめるようにしました。「よくやってるね」「頑張ってるね」といった感じで、短くていいと思います。すると、問題行動ばかり起こしていた生徒も、少しずつ良い行動が増えていった印象があります。問題行動がなくなるほど簡単なことではありませんが、素晴らしいスッテプアップだと私は思っています。少しずつ、焦らないことが大事です。威圧的にクラスをコントロールすることもできますが、それだと生徒たちと心の距離がなかなか縮まらないということと、私は女性なので、たいして迫力を作れないということで、以上のような指導方法をしています。ポイントは、・問題行動の段階に沿って叱り方を変える・良い行動を見逃さずに誉める・1対1で対話するとき、生徒を信頼しているということを伝えるです。
私は、まだまだ生徒指導に関してて手探りで、毎日正解を探していますが、実験のような気持ちで頑張っています。これからもいろいろな本を読み、自分に合っているものは取り入れ、実験の結果をお話できたらと思います。
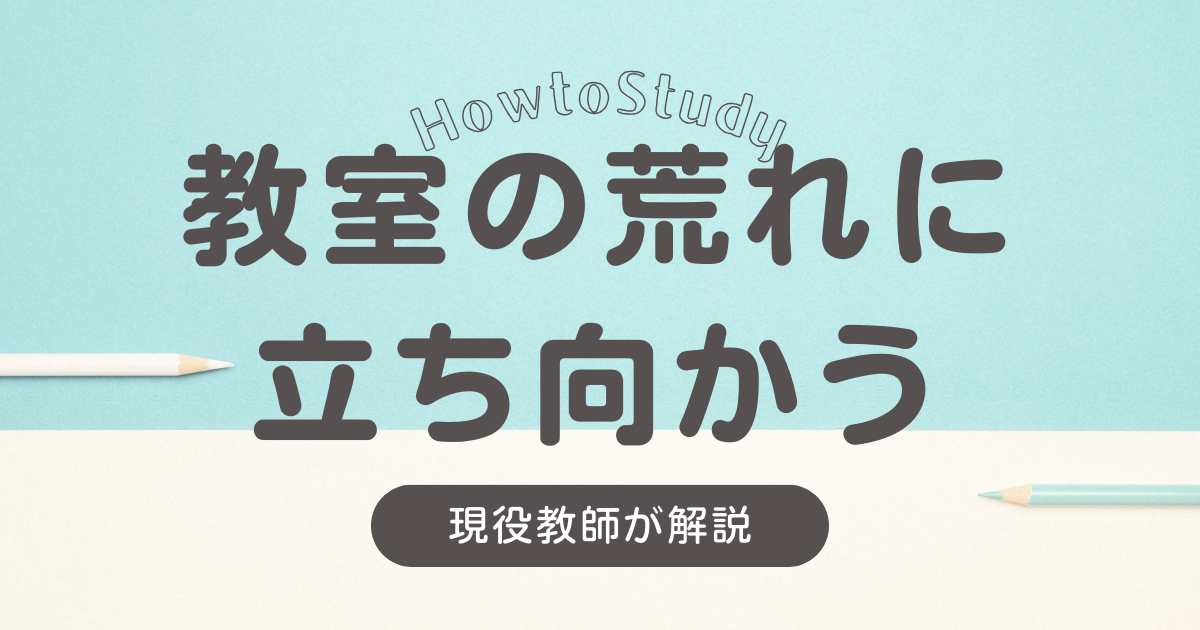

コメント