こんにちは!ココです。
今日は、教室で私が普段から一番気を付けていることについてお話しようと思います。先生が教室で授業を行うことはとても大変なことです。こんな状況には、このアプローチ!などと決まっていないし、状況は本当に様々なので、手探りで試行錯誤しながら自分なりの指導法を見つけていくしかないですよね。私もまだまだ勉強中で、毎日戦いをしているような感じです。正解はないのですが、やはり自分1人だけで戦っていると精神的にも疲れてしまいますし、改善が遅くなってしまう場合もあるので、私は普段から他の先生の話を聞いてみたり本を読んだりして、自分のやり方の中に学んだことを溶かしていくような感じで頑張っています。そんな中でたくさんのアプローチや考え方を学んだのですが、基礎というか、根底にある重要なことは、生徒に主導権を取られないことだと気づきました。なぜ主導権を取られていけないかについて、疑問は湧かないですよね。クラスがコントロール不可能になって、先生の指示が通らなくなるからです。生徒を守るためにも、主導権は先生が持っていなくてはいけませんよね。分かり切っていることですが、少し前まで1番大事なこととして私自身がとらえられていなかったので、その大切さをあなたと自分自身に再確認するために、ブログとして書こうと思いました。これを意識するだけで、クラスでの指導に迷いがなくなると思います。イメージしにくい人もいると思うので、主導権を奪われない方法について、具体的な例もいくつか示してみようと思います。
①生徒から暴言を言われたとき、「落ち着いて」と同じ言葉を繰り返す
荒れているクラスや生徒を受け持つ先生なら、暴言を言われる経験が多くの場合あると思います。そんな時、生徒と言い合いをするべきではないと私は思っています。先生が負けてしまうこともあるからです(笑)。先生だって、何度も生徒と口論をしていたら、負けることもあります。ですが、生徒にとって先生を論破してしまった経験は彼らの心の栄養となり、ますますコントロールが難しくなる場合もあるので、口論をするべきではないと思っています。ではどうすればいいかというと、ひたすら同じ言葉を繰り返し、口論に参加しない姿勢を示すことです。
生徒「うるせーよ!〇〇先生はいいって言ったんだよ!」先生「落ち着いて」生徒「ほんと理解しないな」先生「落ち着いて」生徒「あんたなんか大嫌いだ!!」先生「落ち着いて」
といった感じです。これならどんな言葉を投げかけられてもたじろがずにかわせますよね。私はこれを書籍で知って、実際に口論になりそうになった時に実践したのですが、この言葉を言えばいいだけだと思うと落ち着いて対応することができました。重要なことは、先生が焦ったり感情的にならないことです。さらに、生徒にとっても、自分ばかりが騒いでいると疲れてしまいますし、冷静な先生を前に勢いが落ちてくることもあります。
②問題行動を見つけてもすぐには怒った態度を出さず、少しずつレベルを上げていく
問題行動すべてに全力でかかっていたら先生は自分を縛りつける存在として、生徒は心の距離を広げてしまい、指導が難しくなっていきます。かといってすべての問題行動を見逃していたら、この先生は何をしても許してくれる存在として、この場合もコントロールができなくなっていきます。すごく難しいですよね。ではどうすればいいかというと、問題行動に対して段階的に指導します。
例えば、授業中に自分の席を離れて遊んでいる子がいたら、
①目が合う位置に移動し、ジェスチャー(手招き)をする
②少しずつ距離を詰めていき、肩をポンとたたいてじっと見つめる
➂ 「3回までしか注意しないよ。その間に席に戻ってくれたらうれしいな」などと伝える
④ 廊下に連れ出し、個別で話をする。この時気を付けるべきことは、生徒に全否定していないことを伝えることです。例えば、「なんで先生がいつもあなたに注意するかわかる?あなたがとてもいい子だからだよ。今日は前半の時間はノートちゃんととっていたし、すごいなと思ったよ。でもさっきはどうだったかな・・・」といった感じで、叱るときはどこが良くて、どこがダメだったかしっかり言葉にして伝える必要があります。私は高校教員なので、高校生にこの方法で叱っています。相手の自尊心を傷つけずにダメなところを伝えることができるので、子供だけでなく、大人に対しても効果的な注意の仕方だと思います
①~④と順番にステップを進めていくどこかで、問題行動をやめてくれたらいいですね。たいていの場合はやめてくれるのですが、④番まで丁寧に指導しても直らない場合もあります。私もこれ以上の指導を思い付かないし、地道に毎日同じことを繰り返していますが、そんな中で、問題行動をやめてくれる日もあります。次の日にはもとに戻ってしまいますが(笑)。焦らないで、少しずつ指導を重ねていくだけだと今は思っています。
➂決して生徒の機嫌を取らない
問題行動を起こすような生徒と毎日向き合っていたら、先生も疲れてしまいますよね。当然分かっていることなのですが、ついつい口論や面倒事を起こしたくなくて荒れている生徒に過度に気を遣ってしまうことがありました。生徒を否定しないという思いが、ついつい楽な方へ流れてしまったのだと反省しています。ですが、生徒を認めてあげることと、生徒の機嫌を取ることは全然違いますよね。機嫌をとることを続けていると、それまで真面目に頑張っていた子たちがばかばかしさを感じてしまい、そんな子たちからも心で切られてしまいます。これは絶対に避けたいと思っています。そのためにも、クラス全員平等に、ダメなことはダメと伝え、良いことはほめるようにしています。いくら平等にしていても、生徒たちはひねた受け取り方をすることもあるので、そんな時は先ほどもお伝えした、いい子だから叱るんだという風なことを伝えます。大人しく頑張っている生徒のところのは忘れずにそばに行って、「頑張ってるね。」「分からないところはない?」と、声掛けをすることが大切です。
まとめ
一番重要なことは、生徒に主導権を握られないことです。その具体的な方法として、①生徒から暴言を言われたとき、「落ち着いて」と同じ言葉を繰り返す ②問題行動を見つけてもすぐには怒った態度を出さず、少しずつレベルを上げていく ➂決して生徒の機嫌を取らないことをお伝えしてきました。教室は生きているので、必ずすべての状況に対応するものではないですが、こうした考え方をベースに、先生の軸を作り上げていくことが大事だと思っています。教室ではどんなに準備をしてもうまくいかないことがいっぱいあります。私は毎日が実験だと思って、その結果をブログなどで示していきたいと思っています。

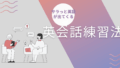

コメント