ある子との出会いから
1年前、私は1年生の英語を授業で担当することになりました。その教室に入った瞬間、最初に声をかけてきたのが、Aさんです。
彼女は私を見るなり、「かわいい」「優しそう!」など、思いつく誉め言葉を言ってくれました。経験上、その子に多少不安定さを感じましたが、このように、距離を一気に詰めてくる感じも愛着障害の特徴の1つだということを、この時は知りませんでした。
この1年の間にAさんに関して大変なことがたくさんありました。最初はすごく人懐こくて、授業のサポートまでしてくれていたような子が、突然態度を一変させます。途中、私はこのままこの教室で授業続けられるのかなと不安になりましたが、様々な本を読み、今は大丈夫です。
その勉強の中で、私と同じような悩みを抱えている先生や、保護者の方がいることが分かりました。
今日は、Aさんの愛着障害(かもしれない)についてお話していきます。
関係が崩れた瞬間
Aさんは人懐こく、英語の時間でも積極的にノートを取ったり、教員の私に話しかけたりしていました。でも、1学期も終わり2学期に差し掛かったあたりから、問題行動が目立つようになってきました。
例えば、授業中スマートフォンを使う、教室を自由に立ち歩く、私語が絶えず授業の邪魔をするなどです。
最初は柔らかく声掛けをして問題行動を指摘していたのですが、それでも直らないので、ある時厳しめの対応をしました。
私の学校では問題行動をすると、訓戒カードにチェックを付けることになっているので、Aさんのカードにチェックを入れたのです。
訓戒のチェックは外せないと悟ったAさんは、次の授業から、私に対して暴言を言ったり、反抗的な態度をとるようになりました。
例えば、私に命令するようなことを言ったり、言うことを聞かないと「バカなんだよ」「私の言うことだけ聞いとけばいいんだ」など、ひどい態度を取り続けました。
関係が修復した瞬間 ポジティブな声掛けをし続ける
そんな状況になってしまってからのAさんのクラスの授業はつらかったです。毎日憂鬱に感じてしまいました。以前にも似たような子の授業を受け持っていて、しんどい思いをしたことがありました。また同じ間違いをしてしまったのかなと思うと、とても悲しくて情けなかったです。
でも、教師ですから毅然とした態度を取り続けないといけないと思い、その状況でも注意するときはしましたし、褒めるときは褒めました(褒める場面を見つけるのはとても大変かもしれませんが、頑張ってその瞬間を待ちましょう)。
最初は「頑張ってるね」などポジティブな声掛けをしても、「黙れ」といって、暴言で跳ね返されていました。そのことは覚悟の上でした。どんなにきつい言葉をかけられても、ポジティブな声掛けをやめてはいけないと思い、不安な中でも頑張り続けました。
Aさんが反抗的になって3週間ほどたった頃、Aさんから私に話しかけてきました。「そのブラウスかわいいね」と自ら声をかけてくれたのです。
私はもうAさんとは関係修復できないんだと思っていたので、Aさん自ら声を掛けてくれたことがとてもうれしかったです。Aさんの機嫌を取るわけではなく、心の距離を縮める努力をしないと指導が全く通らなくなってしまうので、声をかけ続けてよかったと思いました。
気づいたこと:「愛着障害」という言葉
一連の出来事が終わった後、何が原因だったのか調べていく中で、愛着障害という言葉に出会いました。
いくつかの特徴を読んだとき、『Aさんのことかもしれない』と腑に落ちる瞬間がありました。
愛着障害の特徴として、
「言うことを聞かないのに、文句や要求ばかりする」
「今までやってきた対応・指導ではうまくいかない」
「してはいけないことを注意すると、余計その行動の問題が増える」
「激しい暴力行為が突然起き、抑えても収まらない」
― 米澤好史『優しくわかる愛着障害』(ナツメ社, 2022年)
あなたの生徒さんには当てはまりましたか。
愛着障害とは何か
愛着とは、「特定の人に対する情緒的絆」のことで、子供にとって、恐怖や不安から守ってくれる「安全基地機能」、そこに行くと落ち着く、ほっとする「安全基地機能」、そこから離れても大丈夫で、離れて行ったことを報告して認めてもらう「探索基地機能」の3つの機能があります。この絆が育ってない問題が、愛着の問題です。
― 米澤好史『優しくわかる愛着障害』(ナツメ社, 2022年)
私の指導で間違っていたこと
愛着障害の中でも、タイプがいくつか分かれるみたいです。ここでは詳しくお話しませんが、その中で、叱ると余計その行動をしてしまう、抑制タイプというのがあります。本で調べると、Aさんも抑制タイプの部類に入ると思われます。そのAさんに向かって、強い口調で叱ることは逆効果だったのです。
私の指導で良かったところ
Aさんがどんなに私に対して恐ろしい態度をとってきても、声をかけ続けたことはよかったと思います。他人に対して命令口調になってしまったり、暴言を言ってしまったりする子は、相手がそれに対してどんな反応を見せるか、試しているところもあるみたいです。かまってほしいという気持ちもあるので、余裕がない時でも、相手を認めてあげる、受け止めてあげる態度を保ち続けることがとても重要です。
最後に
困難なクラスを受け持っている経験をもとに、これからも授業や生徒指導に関する記事を発信していきます。
指導が難しい子や愛着障害の子は、どんなに一生懸命になっても、なかなか伝わらないです。それでも声をかけ続け、病んでしまうようでしたら演技だとしても、あなたのことを心配してるよ、と伝わるようにすることが重要です。その先で、奇跡みたいにうれしい瞬間が待っているかもしれません。普段は期待せずにお仕事として淡々と頑張りましょう。うれしい瞬間には思いっきり喜びましょう。
このブログでは、これから『愛着障害を持つ子どもとの関わり』『クラス運営での工夫』『教員としてできること・できないこと』などについて、もっと詳しく書いていこうと思います。
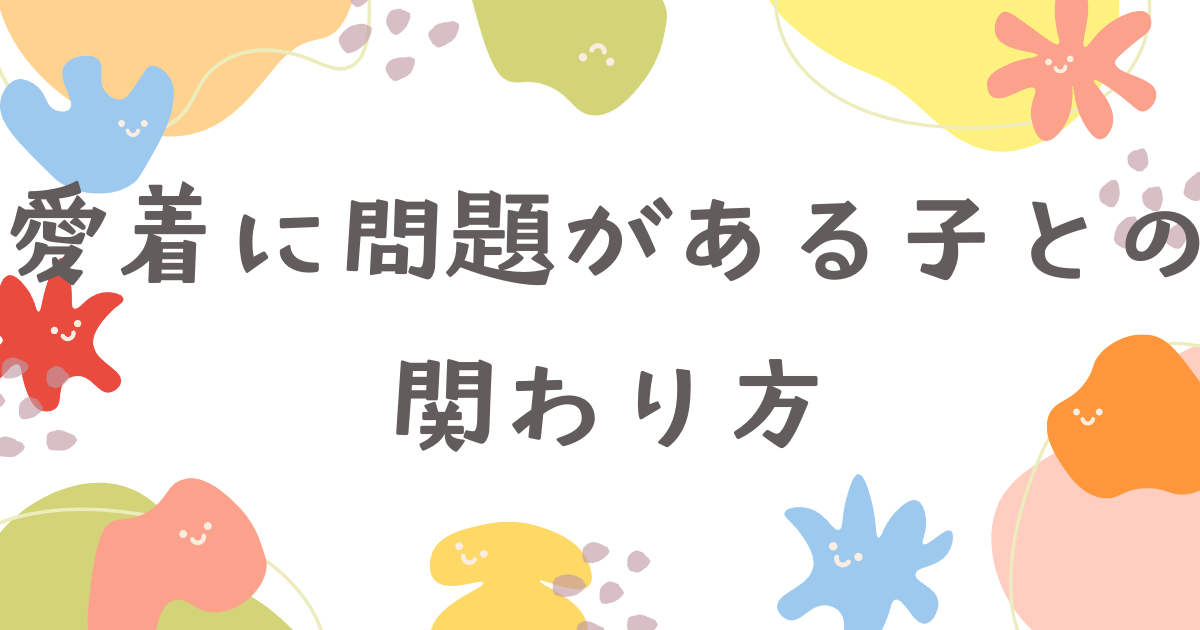
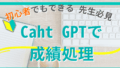
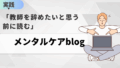
コメント